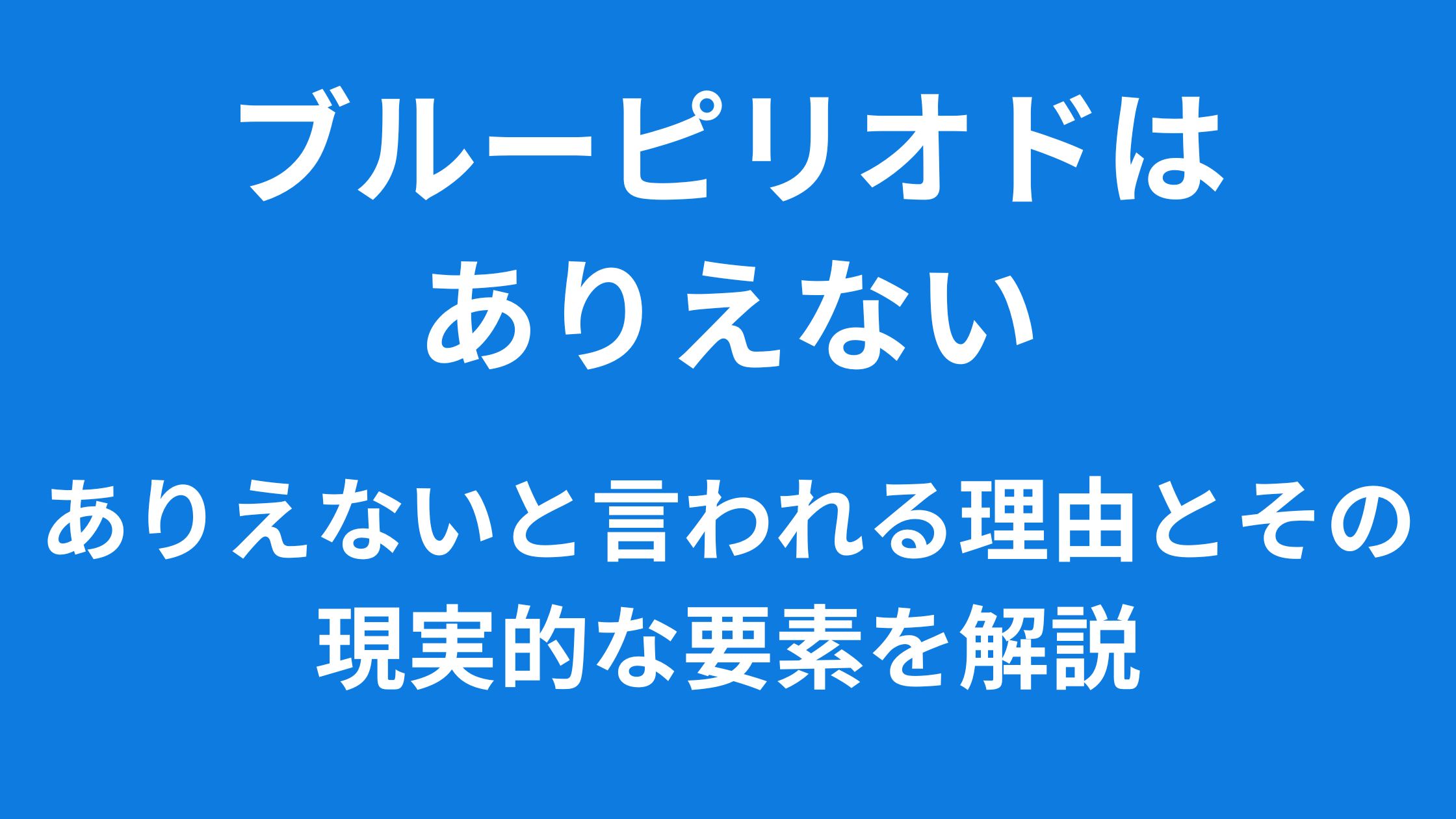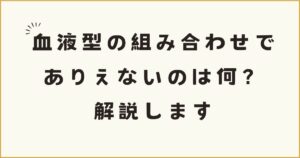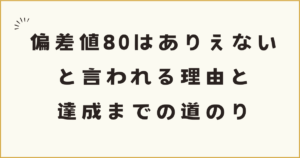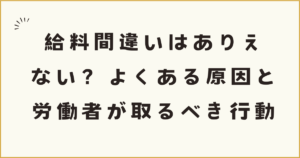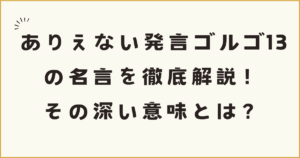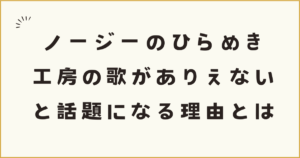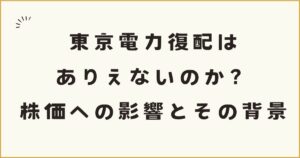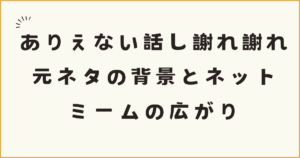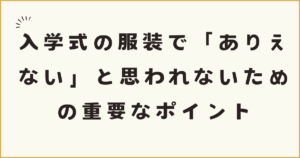『ブルーピリオド』は、美術に無関心だった高校生が東京藝大を目指す物語です。しかし、主人公が短期間で藝大に合格する展開は「ありえない」と感じる人が多いです。
この記事では、その「ありえない」と思われる理由や、漫画やアニメでの違和感、美大生や視聴者の感想を詳しく解説します。
- 『ブルーピリオド』のあらすじと作品の魅力
- 漫画やアニメで感じる違和感や批判の理由
- 藝大合格の難しさと作品内の設定が「ありえない」と感じられる理由
- 美大生や視聴者からの感想や批評の背景
ブルーピリオドの現実とありえない設定

・ブルーピリオドのあらすじと魅力
・漫画とアニメで感じる違和感
・藝大合格の難しさとリアリティ
・美大生の感想と批評
・炎上した理由とその背景
ブルーピリオドのあらすじと魅力
『ブルーピリオド』は、美術に無関心だった高校生・矢口八虎が、美術の魅力に目覚め、美大受験を目指す物語です。
彼は普通の高校生でありながら、美術の世界に飛び込み、東京藝術大学を目指す過程で、仲間との交流や自身の成長を描いています。
この物語の魅力は、単なる「努力と才能」だけではなく、主人公が苦悩や葛藤を乗り越えていく姿にあります。美術を通じて人生に向き合う姿勢が、読者に強い共感と感動を与える作品です。
漫画とアニメで感じる違和感
『ブルーピリオド』は、漫画とアニメの両方で人気を博していますが、両者にはいくつかの違和感が存在します。
まず、アニメではストーリー展開が漫画に比べて早く進むため、キャラクターの心の動きや成長が十分に描かれないことがあります。
特に、八虎が美術に目覚める過程や、彼が感じる葛藤が急ぎ足で描かれるため、視聴者にとっては感情移入が難しいと感じることがあるでしょう。
一方で、漫画では細かな心理描写やキャラクターの内面が丁寧に描かれており、八虎の成長をじっくりと追体験できます。
この違いは、メディアの特性上やむを得ない部分もありますが、原作ファンにとっては物足りなさを感じる要因となることが多いです。
アニメ化に伴う制約が、物語の深みやキャラクターの魅力を損なっていると感じる人も少なくありません。
藝大合格の難しさとリアリティ
東京藝術大学(藝大)は、日本で最も難関とされる美術系の大学です。
その合格難易度は非常に高く、現役合格することは稀なケースです。多くの受験生が中学生の頃から予備校に通い、長い時間をかけて準備を進めますが、それでも一浪、二浪するのが一般的です。
これは、藝大が求めるレベルが非常に高く、単に技術だけでなく、独自の創造性や個性も強く求められるためです。
『ブルーピリオド』の主人公・八虎が、高校2年から美術を始め、わずか1年半で現役合格するという展開は、現実的には非常に稀で、まさに「ありえない」出来事といえるでしょう。
ただし、八虎のような「眠れる才能」を持つ人が存在しないわけではなく、その点ではリアリティも感じられますが、一般的な受験生にとっては、努力だけではどうにもならない壁が存在することを強調しておきたいです。
美大生の感想と批評
『ブルーピリオド』は、美大生や美術を志す若者たちからも注目を集めていますが、その感想や批評はさまざまです。
多くの美大生は、物語のリアリティに共感しつつも、主人公・矢口八虎の急速な成長には疑問を抱いています。
特に、短期間で美術の基礎を習得し、東京藝術大学に現役合格するというストーリー展開は、現実では非常に難しいと指摘されています。
一方で、この作品が美術に対する興味を喚起し、多くの若者が芸術の道を志すきっかけになっている点は高く評価されています。
また、美術の世界の厳しさや競争の激しさをリアルに描いていることから、受験の現実を知っている美大生からは支持される声もあります。
ただし、漫画の展開が理想化されている部分があるため、現実との差を感じる美大生も多いようです。
炎上した理由とその背景
『ブルーピリオド』は、そのリアリティと熱いストーリーで多くのファンを獲得しましたが、一部では炎上も経験しています。
特にアニメ化された際、一部の視聴者から「展開が早すぎる」「キャラクターの描写が不十分」といった批判が集まりました。これにより、原作ファンの期待を裏切る形になり、炎上に繋がったのです。
また、作品内でのキャラクター間の関係性や、繊細な美術表現が一部の視聴者に不快感を与えたことも炎上の原因となりました。
特に、美術大学受験の過酷さを描いたシーンは、実際の受験生にとってはプレッシャーを感じさせる内容となり、批判的な意見が出ることになりました。
これらの要因が重なり、一時的に炎上が起きましたが、作品全体としての評価には大きな影響を与えていません。それでも、アニメ制作の難しさや視聴者の期待に応えることの難しさが浮き彫りになった出来事でした。
ブルーピリオドのありえない要素と賛否

・大学編がつまらないと言われる理由
・絵が下手に見えるキャラクターの描写
・アニメの気持ち悪いシーンへの批判
・映画版に見るブルーピリオドの魅力
大学編がつまらないと言われる理由
『ブルーピリオド』の大学編に入ると、一部の視聴者や読者から「つまらない」と感じられる声が増えることがあります。
その主な理由は、物語のペースが遅くなり、緊張感やスリルが減少するためです。
高校編では、主人公・矢口八虎が美大受験に向けて奮闘する姿が描かれ、その熱意と成長が多くの人を引き込みました。
しかし、大学編に入ると、日常的な学びや課題に取り組む場面が多くなり、ストーリーの進行がゆっくりと感じられます。
また、大学編では新たなキャラクターが多数登場しますが、これらのキャラクターに感情移入するまでに時間がかかることも「つまらない」と感じる原因です。
さらに、美術の専門知識が増えるため、視聴者が理解しにくい部分が出てくることも、物語への関心を薄れさせる要因となっています。そのため、大学編は、高校編と比べるとどうしてもテンポや魅力が失われていると感じる人が多いのです。
絵が下手に見えるキャラクターの描写
『ブルーピリオド』において、一部のキャラクターの絵が「下手」に見えることがありますが、これには意図があります。
物語の中で描かれるキャラクターたちは、美術を学び始めたばかりの初心者から、すでに高い技術を持つ者までさまざまです。特に主人公の八虎が美術に初めて触れる段階では、彼の描く絵が未熟に見えるのは当然のことです。
このような描写は、キャラクターの成長を視覚的に示すための手法です。
最初は不格好であったり、バランスが悪かったりする絵が、彼らの努力とともに次第に改善されていく過程が、作品全体の魅力となっています。
また、技術的に上手な絵を描くことが必ずしも「良い絵」を意味しないことも、この作品を通じて表現されています。
つまり、「下手」に見える絵は、キャラクターの成長や個性を強調するための重要な要素であり、物語のリアリティを高めるための工夫なのです。
アニメの気持ち悪いシーンへの批判
『ブルーピリオド』のアニメ版では、一部の視聴者から「気持ち悪い」と感じられるシーンに対する批判がありました。この批判は主に、キャラクター間の関係性や美術表現に起因しています。
特に、主人公・矢口八虎と高橋世田介の親密なやり取りが、BL(ボーイズラブ)的な要素を含んでいると感じられたため、視聴者の中には不快感を抱く人がいたのです。
また、アニメの美術表現が非常にリアルであるがゆえに、視覚的なインパクトが強すぎると感じる場面もありました。
例えば、美術大学受験の緊張感や、キャラクターたちが追い詰められるシーンがリアルに描かれることで、視聴者の中にはその感情に共感しすぎて「しんどい」と感じる人もいました。
これらの要素が重なり、一部の視聴者からは批判の声が上がることになりました。
映画版に見るブルーピリオドの魅力
『ブルーピリオド』の映画版では、アニメや漫画とは異なる視点で物語の魅力が引き出されています。
映画という媒体特有の表現力が、視覚や音楽といった要素を通じて、物語の感動や美術の世界観をより深く伝えることができるのです。
特に、映画ならではのダイナミックなカメラワークや音響効果が、美術作品の細部やキャラクターの心情を鮮明に映し出しています。
さらに、映画版では限られた時間の中で物語が凝縮されているため、テンポよくストーリーが進行します。その結果、観客は集中して作品の世界に没入できるのです。
また、映画ではキャストの演技が作品に大きな影響を与え、キャラクターに命を吹き込むことで、原作ファンだけでなく初めて作品に触れる人々にも強い印象を与えることができています。
映画版『ブルーピリオド』は、原作やアニメとはまた違った形で作品の魅力を伝えることに成功しており、視覚的・感情的に訴えかける要素が強化されています。
ブルーピリオドがありないと言われる理由や背景まとめ
- 『ブルーピリオド』は美術に無関心だった高校生が美大を目指す物語である
- 主人公・八虎が高校2年から美術を始めて現役で藝大に合格する設定は非常に稀である
- 漫画とアニメで描写の違いがあり、特にアニメは展開が早く感情移入が難しいとされる
- 藝大合格は非常に難関で、多くの受験生が長期間の準備を必要とする
- 現役で藝大に合格することはほとんどなく、多浪が一般的である
- 美大生からは、物語のリアリティに共感しつつも八虎の急成長には疑問の声がある
- 物語が美術に興味を持つきっかけになる点は評価されている
- アニメ化に際して、展開の早さやキャラクターの描写が不十分という批判があった
- 一部の視聴者はキャラクター間の関係性を不快に感じ、「気持ち悪い」という批判もある
- 大学編はテンポが遅く、新キャラへの感情移入が難しいため「つまらない」と感じられる
- キャラクターの絵が「下手」に見えるのは、成長を視覚的に示すための意図的な描写である
- 映画版では、映画ならではの表現力で物語の魅力がさらに引き出されている
- 映画版は視覚と音響効果で感情的に訴えかける要素が強化されている
- 美術大学受験の過酷さがリアルに描かれ、プレッシャーを感じる受験生もいる
- 映画版は原作やアニメとは異なる視点で楽しめる作品となっている